インビザラインの失敗例と失敗しないための対策を徹底解説

この記事の監修者
国井 隆一
くにい歯科・矯正歯科
2021/12/21
2024/7/18
#インビザライン
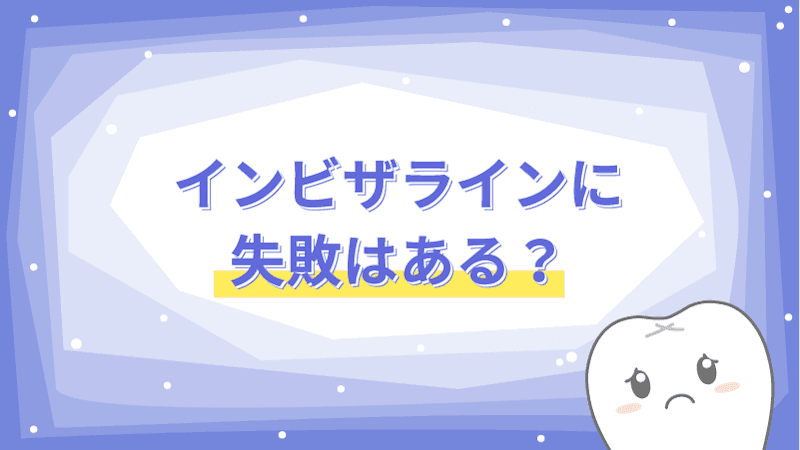
「インビザラインでの矯正が失敗することはないのかな」
「インビザラインで失敗しないためには、どうしたらいいのかな」
インビザラインは、着脱可能・目立たない・痛みが少ない矯正として、近年人気が高まっています。
しかし、「インビザラインは失敗することがある」と知って、利用をためらっている方が多いようです。
実際のところ、ほとんどの失敗は未然に防げます。
この記事では、インビザラインの失敗例と原因から考えられる、失敗しないための対策を紹介しています。
自分が矯正をするときには本記事の対策を活かして、失敗のリスクを減らしていくことが可能になりますよ。
インビザラインを含むマウスピース矯正を検討している方は必見です。
- 2.1【対策1】装着時間を守る
- 4まとめ
インビザラインの失敗例8つと原因
インビザラインは、1999年の誕生から800万人に利用されてきた、実績のあるマウスピース矯正ブランドですが、過去には失敗に終わったケースもあります。
ただし対策をしていれば、ほとんどの失敗は防ぐことが可能。
まずは、8つのインビザラインの失敗例とそれぞれの原因から、矯正で気を付けるべきポイントを確認していきます。

【失敗例1】矯正効果を感じられなかった
最もわかりやすい失敗といえるのが、「矯正効果を感じられなかった」という失敗例。
インビザラインを始めとするマウスピース矯正は、歯並びをきれいにするために利用されます。
インビザラインを用いて治療をしたにもかかわらず、矯正前と矯正後の歯並びに変化がなければ、失敗といえます。
原因
インビザラインで矯正効果を感じられないことの原因は、多くの場合「装着時間の不足」が考えられます。
インビザラインでは、1日あたり20時間以上の装着が推奨されています。
1日に20時間装着することで、1週間に0.25mm、1か月で最大1mm程度歯を動かせます。
装着時間が不足すると、歯に十分な力がかからず、歯列は整っていきません。
【失敗例2】出っ歯になった
インビザラインで歯列の治療を始めたら、矯正が終わる頃には出っ歯になっていた、という失敗例があります。
原因
インビザラインを用いた矯正で、出っ歯になってしまうケースの多くは、無理な非抜歯矯正が原因です。
インビザラインには、抜歯矯正と非抜歯矯正があります。
健康な歯の抜歯を避けたいのは理解できますが、歯を動かすスペースを作るために抜歯をしなくてはいけないことも。
本来抜歯が必要な症状に対して、非抜歯のままインビザラインで歯を動かしていくと、結果的にスペース不足で前歯が押し出され、出っ歯になってしまうのです。
【失敗例3】矯正後に歯並びが戻った
インビザラインで歯を少しずつ動かして、いったんは理想の歯並びに近づいたものの、歯並びが戻っていってしまうことがあります。
原因
矯正後に歯並びが戻ってしまうことの原因は、リテーナーを適切に装着していないことにあります。
インビザラインを含めたマウスピース矯正では、歯を動かしたあとに、「保定期間」に入ります。
保定期間の目的は、動かした歯を新しい位置に固定すること。
動かし終えたばかりの歯は、根元が新しい位置に固定されおらず、根元の組織が記憶している元の位置へ戻ろうとする力が働きます。
そこで、リテーナーというマウスピース型の装置を着けて、歯に新しい位置を記憶させるのです。
保定期間のはじめは、歯の元の位置に戻ろうとする力が強くはたらくため、1日20時間以上のリテーナー装着が必要です。
リテーナーの装着時間が不足することで、一度はきれいになった歯並びがズレていってしまいます。
【失敗例4】歯ぐきが下がった
インビザラインの失敗で、矯正後に歯ぐきが下がってしまった、という失敗例があります。
ひどい場合には、歯根の露出まで見られます。
原因
インビザラインで、歯ぐきが下がってしまう原因として考えられるのは、「力のかけすぎ」。
インビザラインでは、歯に力をかけることで、歯根の骨の吸収と再生を引き起こして、歯列を動かしていきます。
通常であれば、持続的に適切な力をかけ続けることで、吸収と再生のペースが保たれながら矯正が進んでいきます。
しかし、力をかけすぎてしまうと、骨の再生が追いつかず、結果として歯肉が退縮してしまうのです。
インビザラインでは、患者さんの口腔データを元に、販売元のアライン・テクノロジー社によって治療計画の大まかなシミュレーションが作成されます。
そのシミュレーションは、あくまでコンピューター上の計算なので、実際の患者さんの骨格を考慮すると、やや無理な動きが含まれていることがあります。
本来であれば、歯科医師はそのような計画を修正して、歯にかかる力をゆるめなくてはいけません。
しかし、担当する歯科医師の経験や知識が不足していると、無理な動きは治療計画に含まれたままになり、「歯に力がかかりすぎる」といったことが起こってしまうのです。
ただし、適切な矯正計画に基づいて、力をかけているにも関わらず、歯ぐきが下がってしまう場合もあります。
歯ぐきが薄い方に見られることが多いです。
インビザライン矯正中に、歯ぐきが下がっているように感じたら、担当の歯科医師に伝えるようにしましょう。
【失敗例5】噛み合わせが悪化した
インビザラインの失敗例の一つに、「噛み合わせの悪化」があります。
歯並びはきれいになったけれども、噛み合わせが合わなくなったというケースです。
「歯並びが改善しているのに、噛み合わせが悪くなるというのは、矛盾しているのではないか」
と思う方もいるでしょう。
この失敗例は、「見た目の審美性は改善されたが、噛み合わせという機能性が悪化している」ということです。
原因
噛み合わせが悪化する原因の一つが、治療計画にあります。
インビザラインでは、歯科医院で撮った口内のスキャンデータを、販売元の米国アライン・テクノロジー社に送ると、治療のシミュレーションが返ってきます。
そのシミュレーションでは、歯並びをきれいにするためのステップが細かく予測されていますが、噛み合わせの変化の予測は完璧ではありません。
そのため、実際に患者さんの口内を診察した歯科医師が、噛み合わせを考慮しながら矯正計画を調整してきます。
つまり歯科医師が、噛み合わせを考慮して計画を設計しないと、最終的な噛み合わせに不具合が出てしまう可能性があるのです。
【失敗例6】虫歯や歯周病になった
インビザラインで歯列矯正をしていると、虫歯や歯周病になってしまうことがあります。
矯正中に虫歯や歯周病になると、治療のために矯正を中止しなくてはいけません。
虫歯が悪化すると、歯を削って詰め物をするため、歯の形状が変わってしまいます。
つまり、作製したマウスピースがはまらなくなってしまい、再作製が必要になってしまうのです。
原因
インビザラインでの矯正中に虫歯や歯周病になってしまう原因は、口内環境の悪化です。
多くの場合、口内環境の悪化は、矯正中の飲食のルールを守らなかったことから始まります。
食事の際にはマウスピースを外すこと、食後の再装着前には必ず歯を磨くこと、が基本的なルールです。
通常であれば、食後に歯を磨かなくても唾液や飲み物によって、ほとんどの食べかすは流されます。
しかし、食後に歯を磨かず、マウスピースを再装着すると、歯の表面や食べかすを閉じ込めることに。
歯の周辺に残った食べかすには菌が集まり、虫歯や歯周病へとつながっていきます。
また、毎日装着するマウスピースが不潔になったことから、口内環境が悪化していくケースもあります。
【失敗例7】顎関節症になった
インビザラインで歯列矯正を進めていくと、顎関節に痛みを感じるようになったり、顎関節症になってしまったというケースがあります。
原因
原因は、「噛み合わせの変化」にあります。
インビザラインでは、審美性つまり歯並びの見た目は改善されたけれども、噛み合わせに不具合が生じてしまうことがあります。
多くの場合、治療計画を設計する歯科医師が、歯列の移動による噛み合わせの変化を、正しく考慮しきれていないことで発生。
噛み合わせが合わないと、顎に負担がかかってしまい、痛みを感じるようになります。
別のパターンは、マウスピースの厚みに違和感を覚えて、それが顎の痛みにつながること。
インビザラインは技術の進歩により、薄くて丈夫なマウスピースの製造を実現していますが、1枚約0.5mmの厚さがあります。
つまり、非装着時と比較して、上下の歯が約1cm早く接触することになります。
患者さんによっては、上下の歯の接触頻度が高くなり、顎に違和感が生じることもあります。
【失敗例8】知覚過敏になった
インビザライン治療の過程で、知覚過敏になってしまう失敗例があります。
歯の最も外側がエナメル質、その内側にあるのが象牙質です。
何らかの理由で象牙質が露出したり、表面に近づくことで、刺激に対して敏感になっている状態を知覚過敏といいます。
原因
考えられる原因は、IPRやディスキングと呼ばれる、矯正過程における歯を削る処置。
歯列矯正では、抜歯によりスペースを確保する以外に、歯の一番外側にあるエナメル質を削って少しのスペースを作る場合もあります。
基本的には、矯正で削るのはエナメル質のみであるため、象牙質が露出することはありません。
しかし、切削範囲が少し大きくなってしまった場合に、象牙質が表面に近くなり、知覚過敏を引き起こしてしまうことがあります。
インビザラインで失敗しないための対策7選
ここまでは、インビザラインの失敗例とそれぞれの原因を紹介してきました。
実は失敗のほとんどは、対策によって防げます。
ここからは、インビザラインで失敗しないための対策を7つ紹介していきます。

【対策1】装着時間を守る
インビザラインでの矯正において、失敗しないために最も大切なことは、装着時間を守ることです。
1日あたり20時間以上の装着がマスト。
食事と歯磨きの時間以外は、常に装着することを意識しましょう。
矯正を始めたばかりで、インビザラインを装着しての生活に慣れない間は、20時間の装着は難しいかもしれません。
短い装着時間から、徐々に時間を延ばしていくことが大切です。
インビザラインを含む、マウスピース矯正の装着時間と効果の関係については、「マウスピース矯正に効果はある?失敗させない方法3選も紹介」でも解説しています。
【対策2】決められた交換の順番とタイミングを守る
インビザラインでは、10日に1回の頻度で、新しいアライナー(マウスピース)に交換していくことで歯を動かしていきます。
アライナーは治療開始から完了までに約50枚必要。
そのすべてに順番が決まっています。
順番どおりに交換していくことで、少しずつ歯並びを理想の形へと近づけていくことが可能なのです。
例えば、順番を守らずに、交換時に3つ先のアライナーを着用し始めるとどうなるのでしょうか。
歯列は3つ先のアライナーを受け入れられる位置にないため、装着するだけで痛みが生じる可能性があります。
同時に、歯周組織や歯根を傷つけている可能性も。
交換のタイミングについても、歯科医師に指定された頻度を守らないと、歯列を傷つけてしまい、矯正が失敗する可能性が高くなります。
矯正は時間がかかるもので、極端なショートカットは失敗のもとです。
インビザラインで矯正を始めたら、決められた順番とタイミングでアライナーを交換していきましょう。
【対策3】リテーナーの装着まで徹底する
インビザラインを利用した矯正では、リテーナーの装着まで気を抜かないようにしましょう。
せっかく歯を少しずつ動かして、歯並びがきれいになっても、リテーナーの装着をサボってしまうと、歯列は後戻りしてしまいます。
特に歯を動かし終えたあとすぐの時期は、歯が元の位置に戻ろうとする力が強くはたらきます。
きれいになった歯並びに満足し、保定期間に入ってすぐ、リテーナーの装着をサボってしまうと、どんどん歯列がズレていくことに。
矯正後の後戻りに対しては、「今まで使ったアライナーで戻った分動かせばいい」と思いがちですが、実はそうではありません。
後戻りは必ずしも「巻き戻し」のように、歯が動いてきたルートをそのまま戻るわけではないのです。
つまり、今まで使ってきたアライナーがはまらず、再作製になる可能性が生じます。
手間も時間もかかってしまいますので、せっかく手に入れたきれいな歯並びを手放さないように、リテーナーの装着まで徹底しましょう。
【対策4】口内環境は清潔に保つ
インビザラインでの矯正を失敗させないためには、口内環境を清潔に保つことが重要です。
なぜなら、口内環境の悪化は、虫歯や歯周病につながってしまうからです。
食事の際はアライナーを外し、食後は歯磨きをして再装着することが鉄則。
装着したままの水分補給は、極力水に限定しましょう。
また、口内環境を清潔に保つには、矯正器具のクリーニングも欠かせません。
インビザラインのクリーニングについては、次の項目で解説してきます。
【対策5】アライナーのクリーニングをする
毎日装着するアライナーのクリーニングも、口内環境を清潔に保つために欠かせません。
食後は歯磨きをすることで、食べかすが歯とアライナーの間に残らないようにすることが鉄則です。
しかし食後の歯磨きを徹底しても、毎日長時間口の中に入れているアライナーは、クリーニングをしないと細菌の温床になってしまいます。
最も重要なメンテナンスは毎日の洗浄。
毎日の終わりに、歯ブラシと歯磨き粉を使って磨きます。
週に1,2回はクリーニング剤を使用しての洗浄。
インビザラインからは専用のクリーニング剤「インビザライン・クリーニング・クリスタル」が販売されています。
虫歯や歯周病によって矯正を失敗しないよう、アライナーのクリーニングで口内を清潔に保つことを覚えておきましょう。
【対策6】必ず定期通院をする
インビザラインで矯正をしている間は、定期的な通院が欠かせません。
頻度は月に1回程度。
なぜなら定期通院の際に、歯科医師は歯が計画どおりに動いているかを確認するからです。
インビザラインでは、矯正前にシミュレーションして治療計画を設計しますが、歯は予想外の動きをすることもあります。
歯科医師は、定期通院の際に、計画からのズレを察知し、修正していきます。
逆に定期通院をサボってしまうと、歯の動きが計画からズレても、そのまま矯正が進んでしまい、修正は困難に。
インビザラインでの矯正を失敗しないようにするには、定期通院をサボらないことが大切です。
【対策7】信頼できる歯科医師を探す
実は、矯正前からできる、インビザラインを失敗させないための対策があります。
それは、「信頼できる歯科医師を探す」ことです。
インビザラインには専用の3Dスキャナーやシミュレーションソフトがあり、アライナーの製作も海外の工場でおこなわれます。
一見すると、歯科医師が治療に直接関わる部分は少ないようです。
しかし、インビザラインでの矯正を成功させるには、歯科医師の高度な知識と経験が必要。
なぜなら、矯正計画を設計する時点で、歯の動きや抜歯必要性などを考慮できないと、理想の歯並びを実現することは困難だからです。
もしくは、今回の記事で紹介したような、見た目の代わりに機能性が失われるといった失敗が起きてしまいます。
専用の装置やシステムに頼ることで、十分な知識を持ち合わせない歯科医師が、インビザラインを扱っている場合もあります。
失敗をしないためには、自分が信頼できる歯科医師を探すことが重要です。
インビザラインの知識を持つことが大切
インビザラインを用いた矯正では、歯科医師の高度な技術と経験が求められます。
それでは、信頼医師を探すにはどうすればよいのでしょうか。
答えは、患者さん自身が、インビザラインや歯科矯正についての知識を持つことです。
もちろん歯科関係者ほどの知識を獲得するのは困難でしょう。
しかし、歯科矯正の進み方や抜歯・非抜歯矯正の選択など、最低限の内容を知っておくだけでも違いがあります。
カウンセリングで一方的に話を聞くだけでなく、自分から質問ができます。
少ない知識でも、自分の持っている知識と歯科医師の話を照らしあわせて、納得がいかなければ、さらに質問を追加したり、セカンドオピニオンを得ることも可能です。
当サイトでは、矯正を検討している方々にとって役立つ知識を紹介しています。
まずは、「コラム一覧」から気になる記事を選んで、知識を身につけていきましょう。
自分の治療について知ることが、インビザラインで矯正をさせることへの第一歩です。
まとめ
インビザラインは、失敗してしまうことがあります。
しかし、ほとんどの失敗は防げます。
矯正中は、アライナーやリテーナーの装着時間や交換のタイミングなど、基本的なルールを守ることが大切。
装着のルールを破ってしまうと、正しく歯が動かず、失敗につながってしまいます、
歯磨きやアライナーのクリーニングを徹底することも、守るべきルール。
サボってしまうと、口内環境は悪化し、虫歯や歯周病になってしまいます。
定期通院は、歯科医師が進捗を確認する貴重な機会なので、欠かさないようにしましょう。
そして、インビザラインでの矯正を失敗しないために重要なのが、歯科選び。
当サイトではインビザライン矯正が受けられるおすすめの医院を紹介していますので、ぜひご覧になってみてください。
この記事の監修者

国井 隆一
経歴
2001年3月 日本大学松戸歯学部卒業 2001年4月 日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座入局 2006年4月 日本大学助手(日本大学松戸歯学部歯科矯正学講座) 2008年11月 日本矯正歯科学会「矯正認定医」取得 2010年5月24日 栃木県宇都宮市にて「くにい歯科矯正歯科開院」
新着記事

おすすめしたい矯正歯科医院について

インプラント治療で歯がない期間は?対処法やよくある質問への回答も紹介

最少4本のインプラント治療「オールオン4」とは?費用や治療の流れも解説

インプラント治療を受けているとMRIは受けられない?安全性や注意点について解説!

インプラント治療は痛い?痛みの程度や対処法について解説
関連する記事
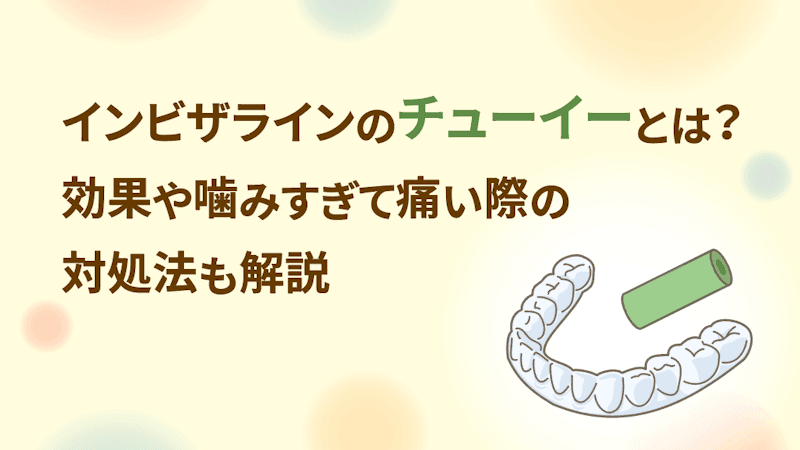
インビザラインのチューイーとは?効果や噛みすぎて痛い際の対処法も解説
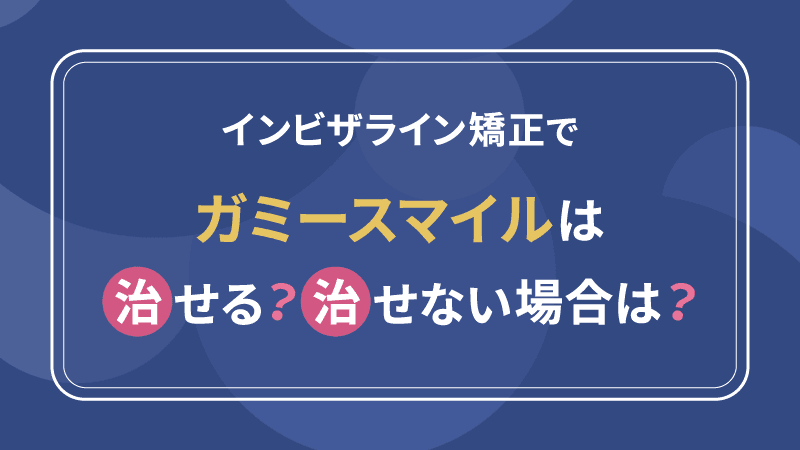
インビザライン矯正でガミースマイルは治せる?治せない場合は?
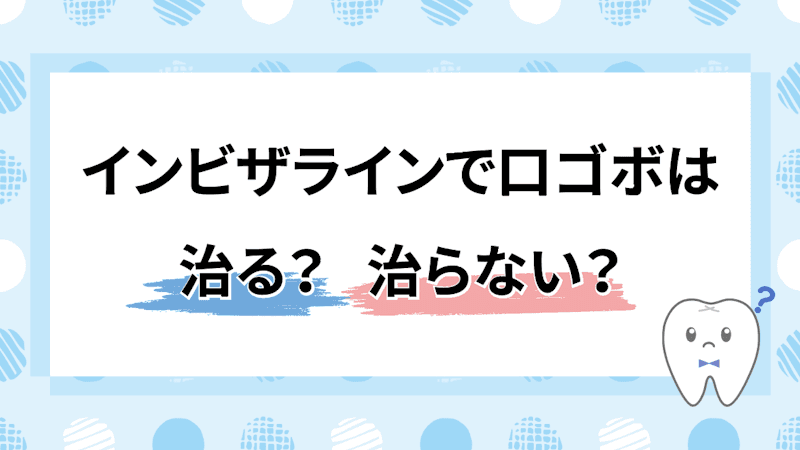
インビザラインで口ゴボは治る?治らない?
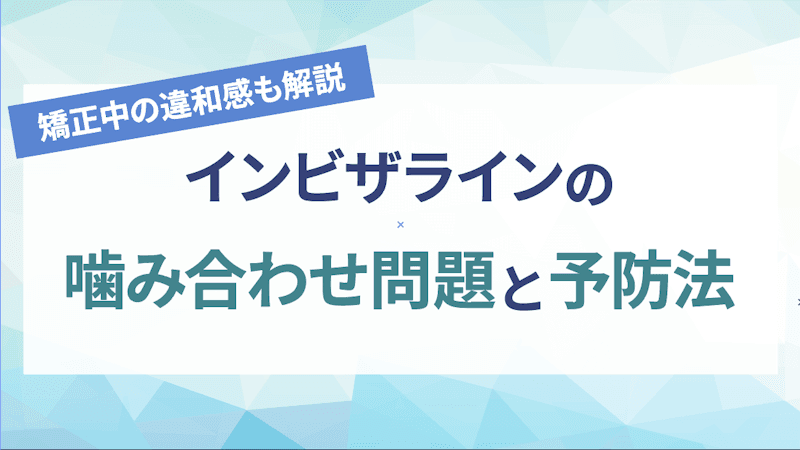
インビザラインの噛み合わせ問題と予防法|矯正中の違和感も解説
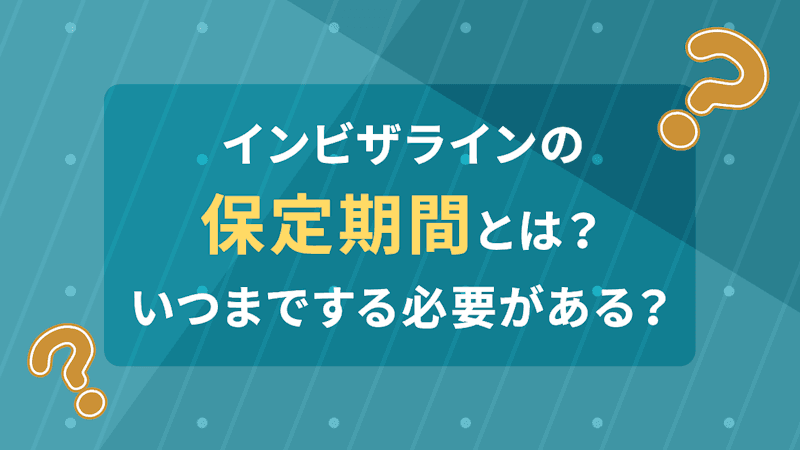
インビザラインの保定期間とは?いつまでする必要がある?
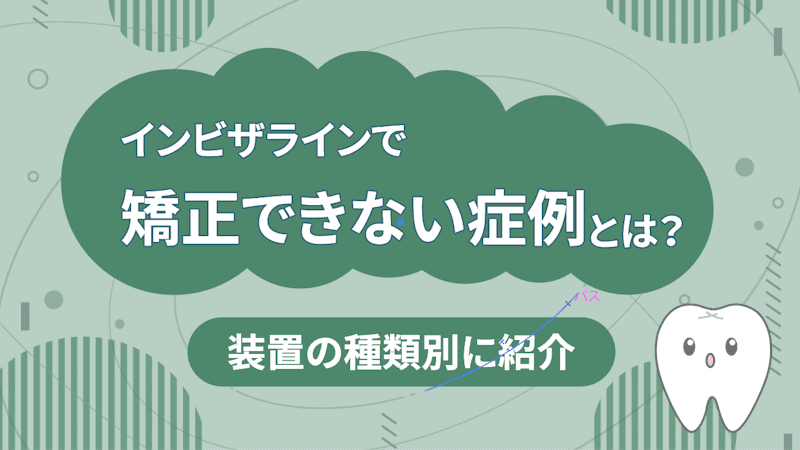
インビザラインで矯正できない症例とは?装置の種類別に紹介
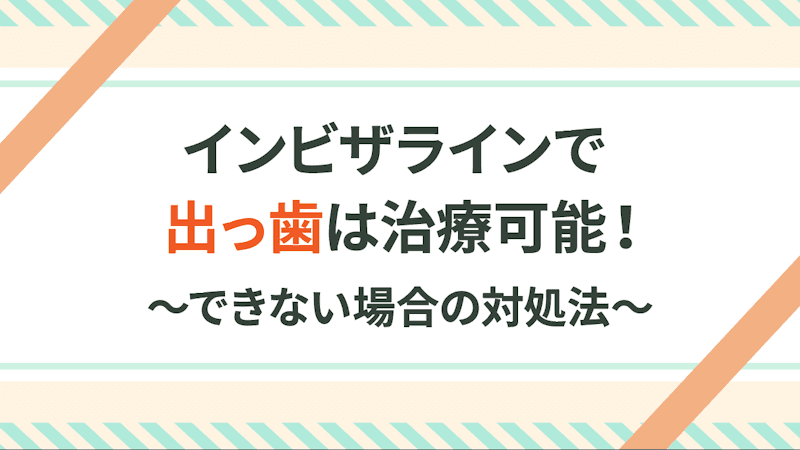
インビザラインで出っ歯は症例により治療可能。できない場合の対処法。
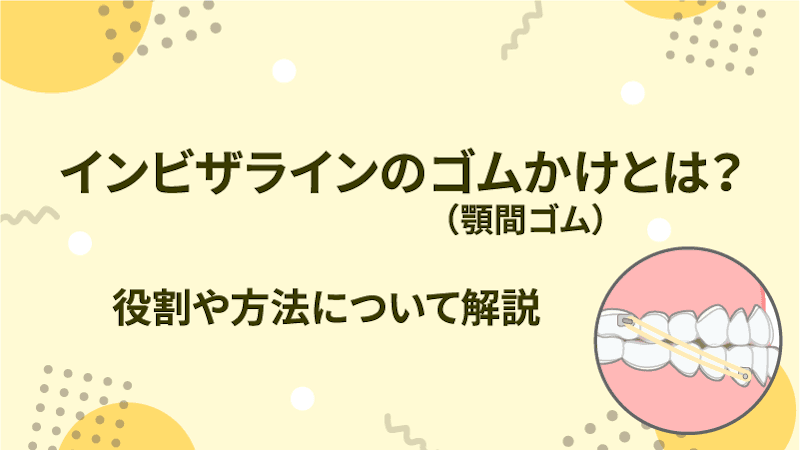
インビザラインのゴムかけはいつからやるの?その効果と痛みの対処法は?
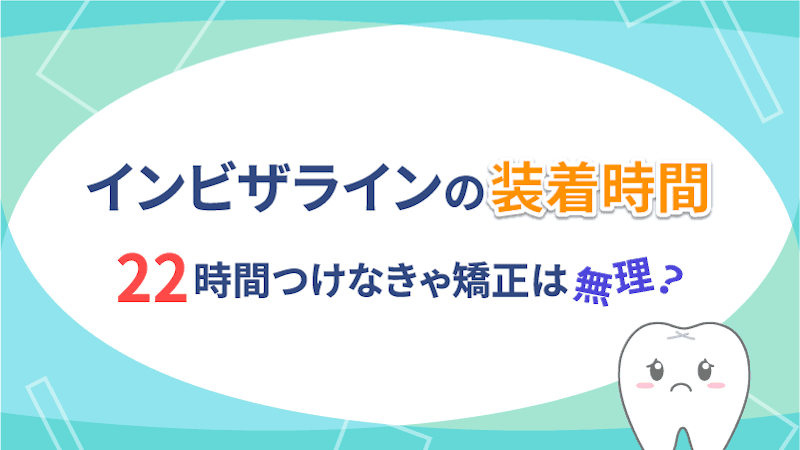
インビザラインの装着時間が守れない!22時間つけなきゃ矯正は無理?
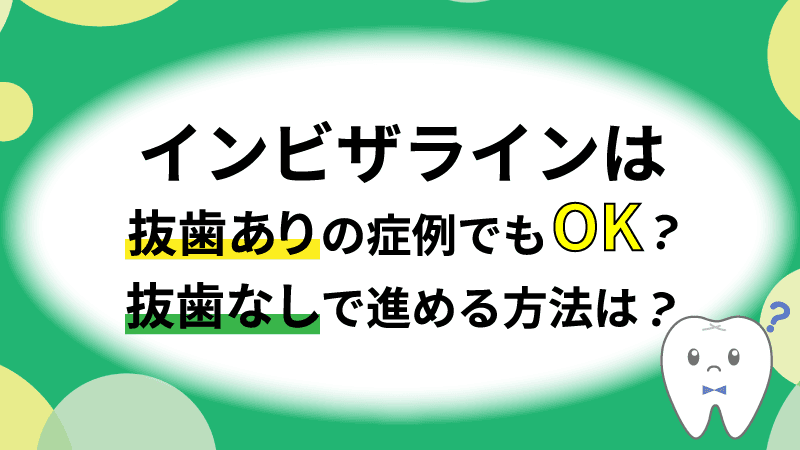
インビザラインは抜歯ありの症例でもOK?抜歯なしで進める方法は?
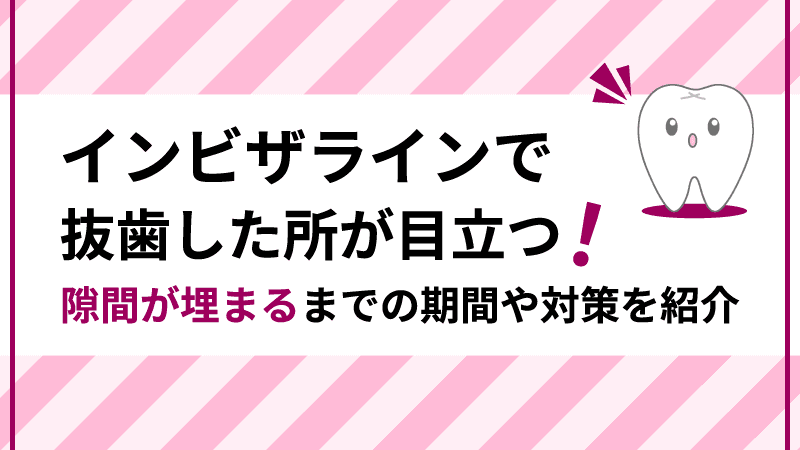
インビザラインで抜歯した所が目立つ!隙間が埋まるまでの期間や対策を紹介
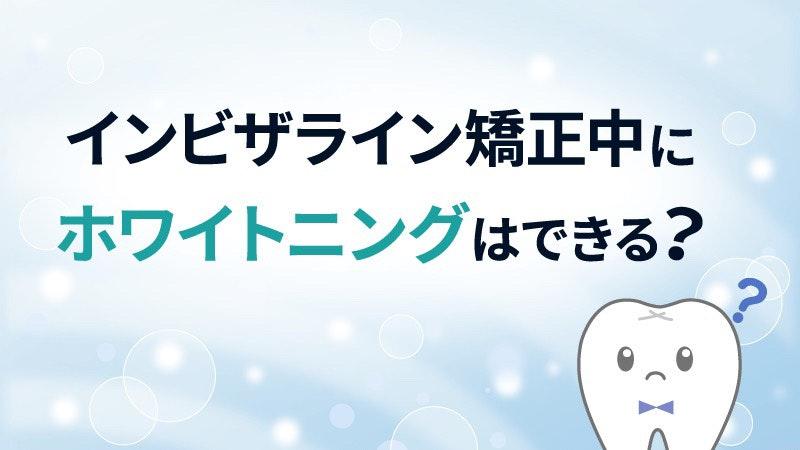
インビザライン矯正と同時にホワイトニングは可能?いつから始めるべき?
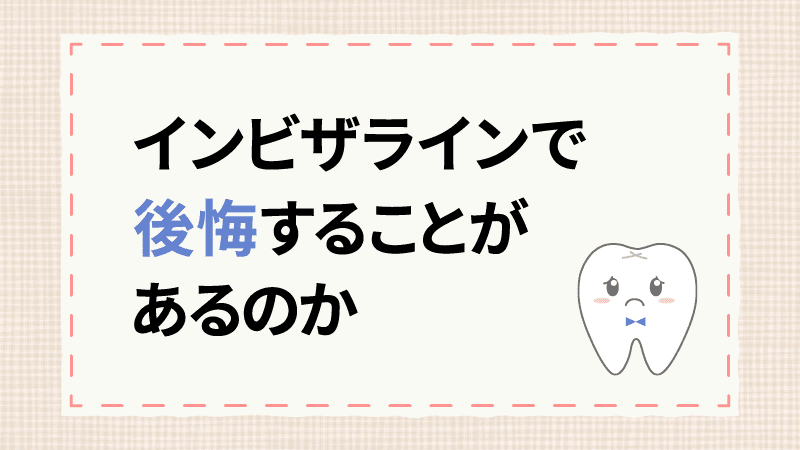
インビザラインで後悔?実際の声とその予防・対処法を公開
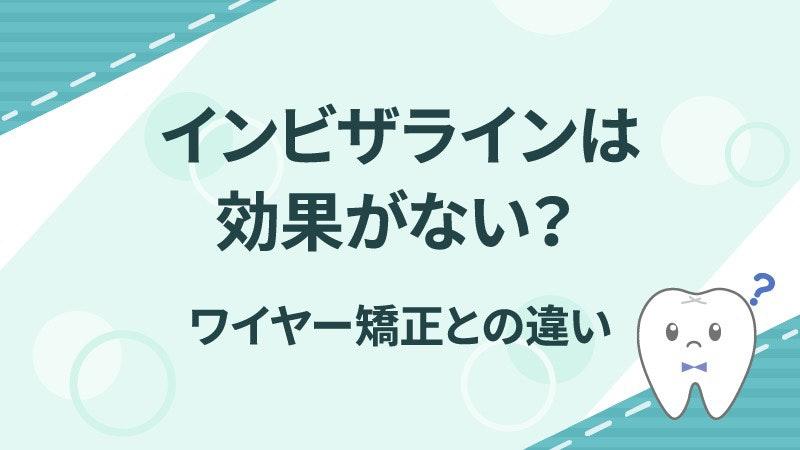
インビザラインは効果がない?ワイヤー矯正との違いも解説
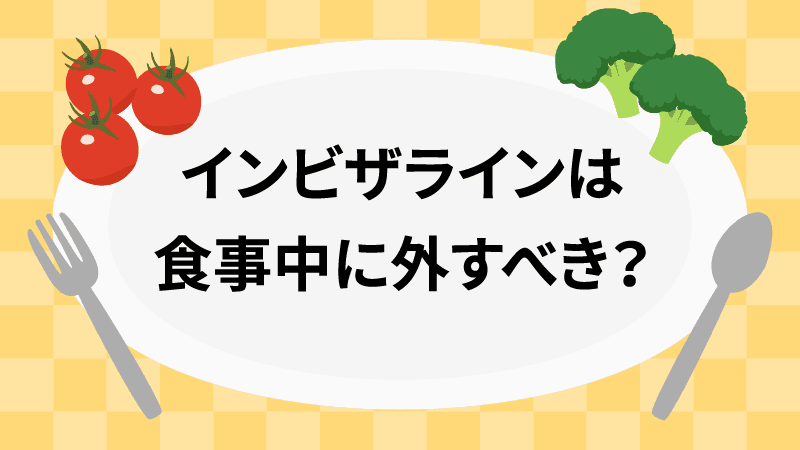
インビザラインは食事中に外すべき?理由や注意点を解説
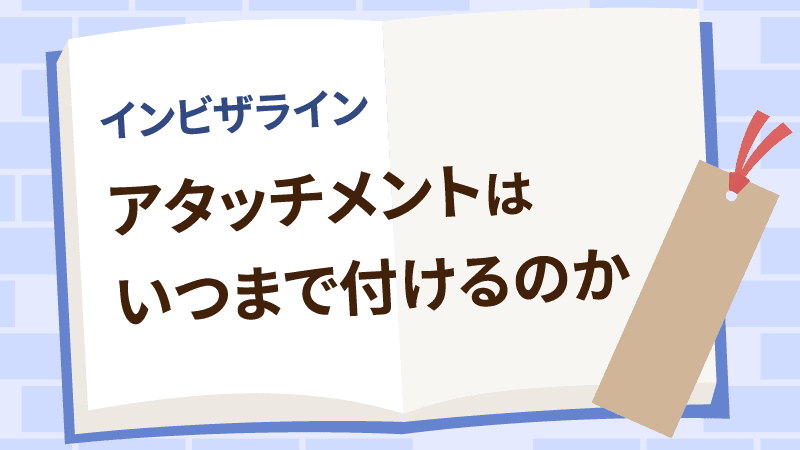
インビザラインのアタッチメントはいつまで付ける?
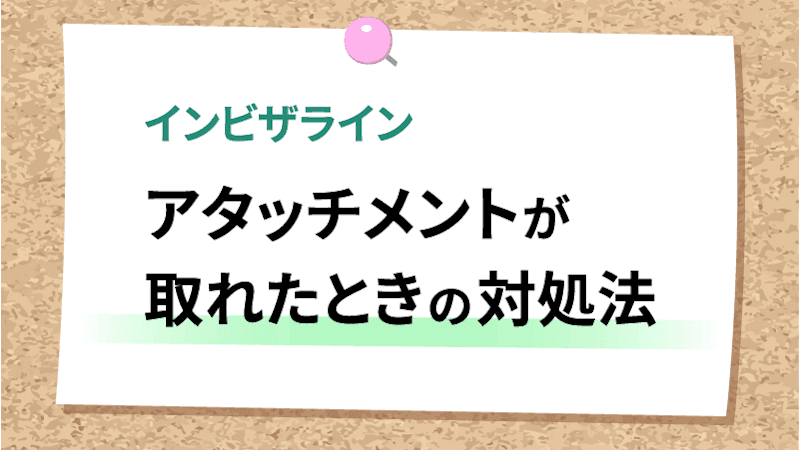
インビザラインでアタッチメントが取れたときの対処法を解説
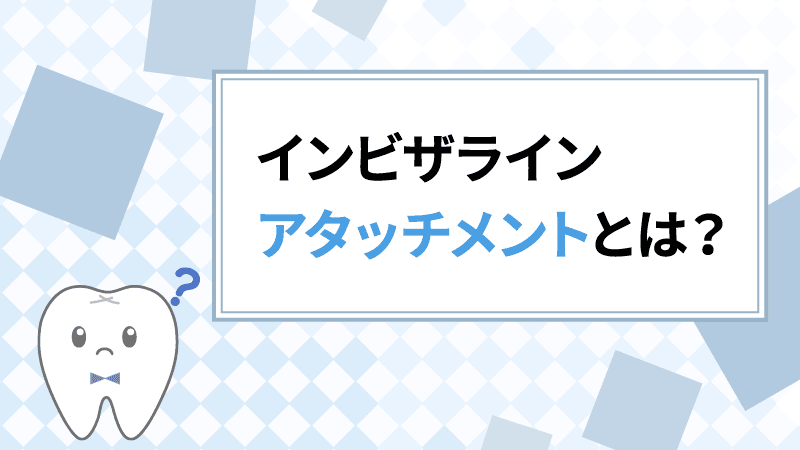
インビザラインのアタッチメントとは?知っておきたい目的や効果などを解説
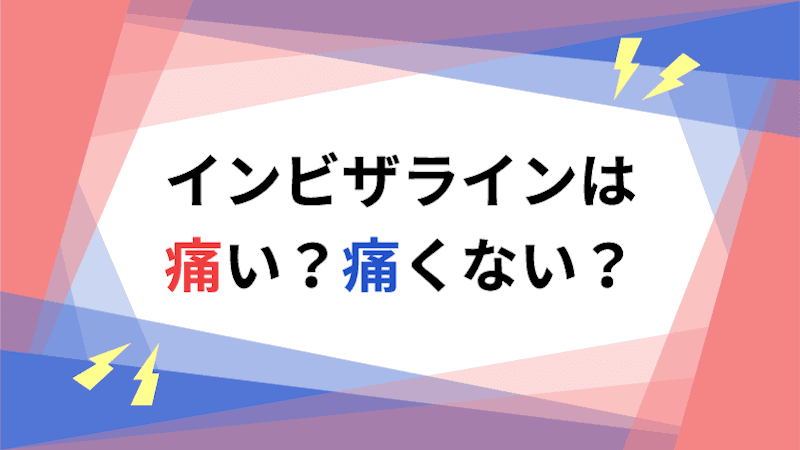
インビザラインは痛いのか|9パターンの痛みと対処法を解説
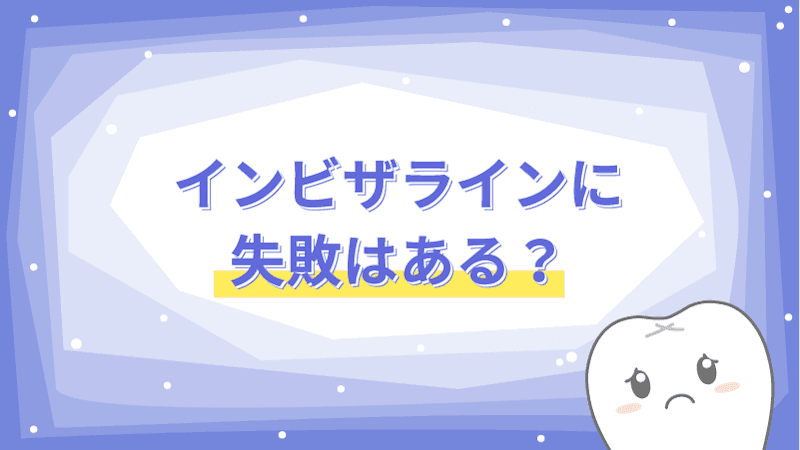
インビザラインの失敗例と失敗しないための対策を徹底解説




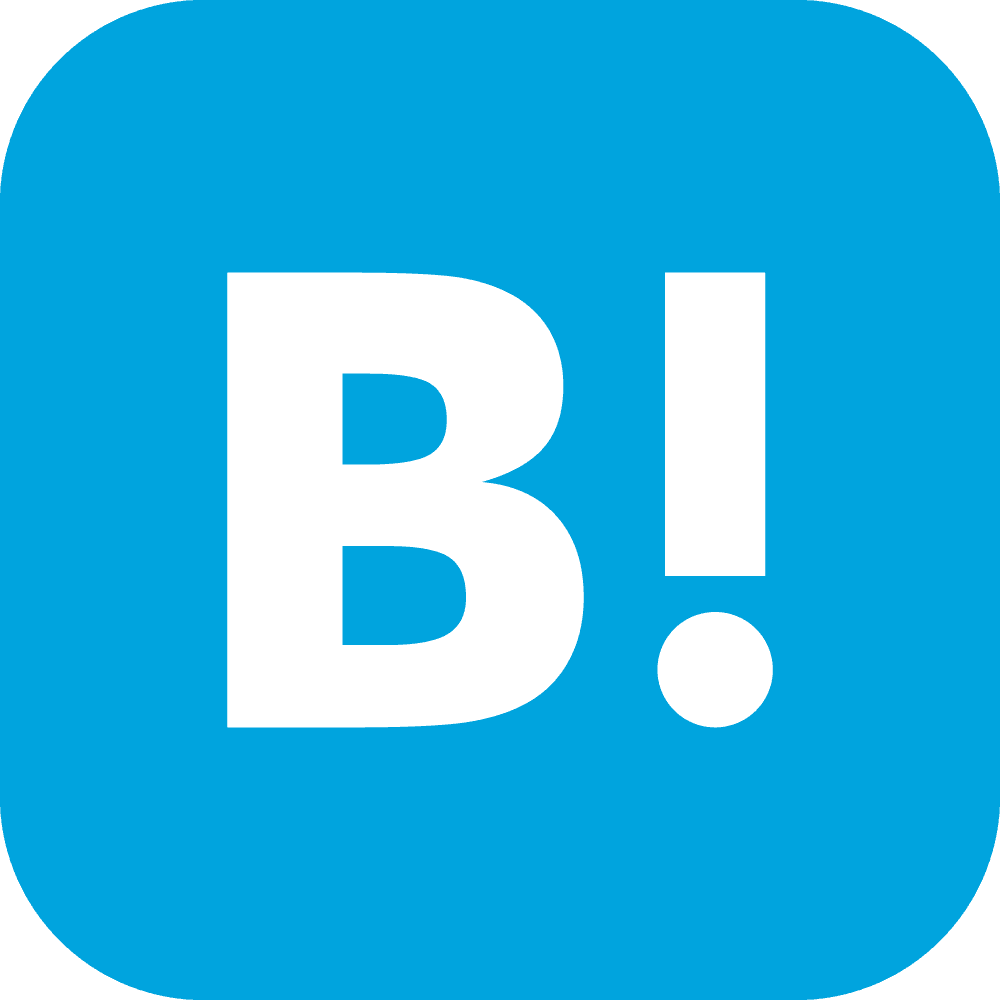
コメント
矯正治療では、審美面の改善はもちろんのこと、噛む能力も向上させることが可能です。ものをしっかり噛むことで消化を助けたり、歯の清掃性を高めることにもつながり、患者様の心身の健康に寄与できるよう日々診療しています。